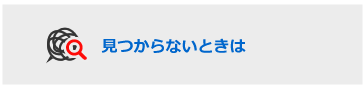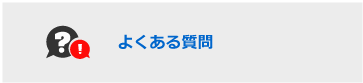児童手当制度とは
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定と、児童の健やかな成長を目的としています。
児童手当制度の概要
支給対象
手当は18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代の児童)を養育している方に支給されます。
(注)
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給額
3歳未満【第1子、第2子】
15,000円
3歳未満【第3子以降】
30,000円
3歳以上高校生年代【第1子、第2子】
10,000円
3歳以上高校生年代【第3子】
30,000円
支払時期
手当は、偶数月にそれぞれの前月分までが支払われます。
支給方法と支給日
手当は、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
4月10日(2月~3月分)、6月10日(4月~5月分)、8月10日(6月~7月分)、10月10日(8月~9月)、12月10日(10月~11月)、2月10日(12月~1月)
※支給日が金融機関休業日にあたる場合は、その後の営業日になります。
手当を受けるには申請(認定請求)が必要です
手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、申請が必要です。
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた等、手当額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内申請が必要です。
他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。(公務員は、勤務先から支給されます。役場と勤務先に届出・申請をしてください。)
(注)
- 里帰り出産等の事情により、出生届を住民登録のある市区町村以外で提出した場合、その場で児童手当の申請をすることができず、改めて住民登録のある市区町村でしなければなりません。(児童手当の申請は、住民登録のある市区町村でしか行えません。)
- 手当の受給者である父母などが拘禁されたときは、受給者を変更するために届出・申請が必要ですので、必ず遅れずに手続きを行ってください。
- 災害、長期入院などやむを得ない理由で申請ができなかった場合は、その理由がやんだ日の翌日から15日以内に申請してください。
詳しくはこども家庭センターまで(ただし、公務員の方は各勤務先まで)
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 申請者名義の金融機関の口座番号などがわかる預金通帳のコピー
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類
- 申請者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書(厚生年金、共済年金などの加入者の場合のみ)
- 認印
その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
マイナンバーカードなどの掲示により課税証明書や住民票などの書類を省略できるようになりました。
児童手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出などが必要です。
現況届
現況届は、毎年6月1日における状況を把握し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。一部の方を除き、現況届の提出が不要となります。
離婚や離婚前提の別居などにより、受給者が児童を養育しなくなったとき
離婚協議中で父母が住民票を別にしている場合は、児童と同居している方が優先されます。手続きには、離婚協議中である事を確認できる書類が必要です。
父母のうち生計中心者が変わったとき
受給者が町外に転出するとき
受給者や児童が亡くなったとき
受給者または児童の姓が変わったとき・児童の住所が変わったとき
届出が遅れ、または届出を怠り、そのまま手当を受けた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。